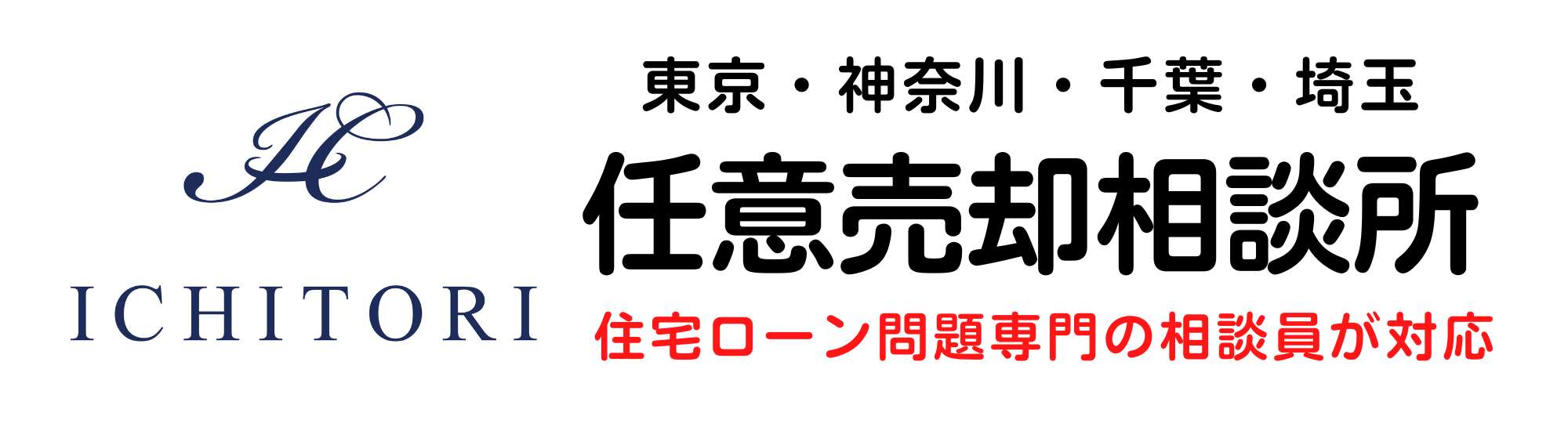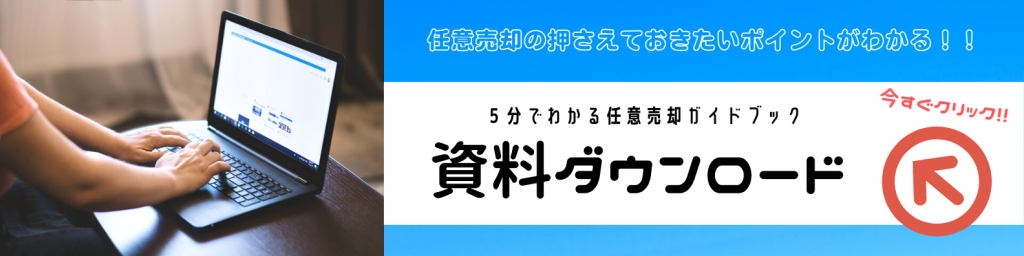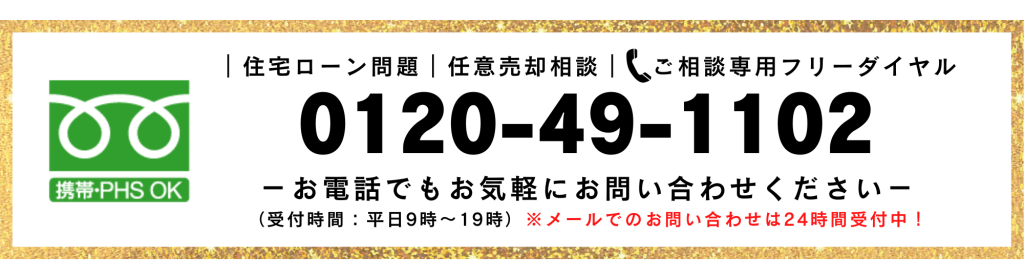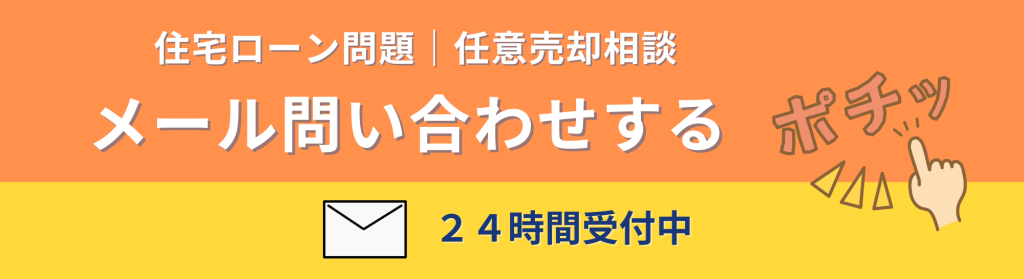固定資産税を滞納したら?延滞税や差押えなどの流れを紹介

例年、この時期になると、土地や建物などの不動産を所有されている方には、「固定資産税」に関する納税通知書が当該不動産が在する自治体より送られてくるかと思います。固定資産税の税額は、かなり大きな金額になることも多く、毎年のように頭を抱える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とはいえ、固定資産税を滞納すると、そこに新たに延滞税が付加されることとなり、最悪の場合、財産を差押えられたり、公売申立てをされたりして多大な不利益を受けることにもなります。
本記事では、固定資産税を滞納した場合に課される延滞税や、不動産などの財産差押えなどについてわかりやすく解説します。

株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
固定資産税について
まずは、固定資産税とはどのような税金なのかということについて説明いたします。
固定資産税とは、固定資産を所有されている方に課せられる地方税(市町村税)で、一般的な財源として使用される普通税(税収の使途が定められていない税)になります。
固定資産税は、徴収した市町村がその使用用途を決定し、例えば、生活で利用する道路、学校、公園、公共施設の整備のほか、介護・福祉などの行政サービスなどにも使われており、そこで暮らす地域住民の日々の生活を支える財源として活用されています。
そして、ここでいう「固定資産」とは、土地、家屋、償却資産を総称したものであり、細かく見ていくと以下のようなものになります。
【固定資産】
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。但し、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く
※償却資産についてより詳しく知りたい方は▶こちら
(東京都主税局サイトへ移行します)
固定資産税の税額について
では次に、固定資産税の税額がどのように決定されるのかを見ていきましょう。
固定資産の価格(評価額)
固定資産税の税額を算出するため、対象の固定資産には価格(評価額)がつけられますが、この固定資産の価格とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、知事または市町村長が一つ一つの固定資産を評価して価格の決定がなされます。
評価方法は土地や家屋、償却資産ごとに異なり、それぞれの評価方法は次のとおりです。なお、土地や家屋の固定資産は、3年に一度評価の見直しが行われます。
宅地や農地の地目別(地目とは、それぞれの土地をその用途によって分類したもの。例えば「田」や「畑」や「宅地」など)に、売買実例価格などを基礎として評価額を計算する。なお「宅地」については、地価公示価格などの7割を目途に評価額を計算する。
再建築価格(評価対象となる家屋と同一のものを、評価時点において、その場所に新築するとした場合に必要となる建築費)に、経年減点補正率など(家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率)に乗じて評価額を計算する。
償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過した年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を計算する。
課税標準額の決定
さて次に、前述した方法で算定された固定資産の価格(評価額)に基づき、賦課期日(1月1日)時点の資産価格を決定します。これが、「課税標準額」となります。
またここで、納税者に対して急激な負担がかからないように配慮を行い、評価額に対して低い場合や、評価額が急激に上昇した場合でも、税負担をゆるやかに上昇させるように、負担調整措置という仕組みが講じられています。なお、場合によっては特例措置(課税標準額を減少させる措置)が適用されることもあります。この特例措置には、例えば、次のようなものがあります。
【住宅用地特例】
住宅やマンションなど、居住できる建物の敷地を「住宅用地」といいますが、住宅用地は税の負担を特に軽減する必要があるため、その面積によって特例措置が講じられています。
200m2以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減され、200m2を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。
固定資産税評価額は、土地であれば、その所在地や面積・形状などによって、また、建物であれば、建物の規模・構造や築年数などによって変わります。
一応の目安としては、土地であれば時価の70%相当額、建物であれば工事代金の50%~60%相当額となっています。具体的な固定資産税評価額は、毎年4月~6月頃に送られてくる「納税通知書」で確認することができます。なお、「納税通知書」の発送時期は各自治体によって異なります。
固定資産税の税額
最後に、実際に私たちが支払う固定資産税の税額です。
最終的な税額は、前述の「課税標準額」に対して、税率(原則1.4%)を掛けた額が固定資産税額となります。しかし、市町村は必要に応じて、1.4%と異なる税率を条例で定めることができることとなっています。計算式で表すと、以下のとおりです。
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
また、場合により減額措置(税額を減少させる措置)が適用されることもあります。この減額措置には、例えば、次のようなものがあります。
【新築住宅特例】
令和6年3月31日までの間に新築された住宅には、減額特例が適用されます。特例の内容は、一般住宅と長期優良住宅(長期に使用するための構造や設備を備えている住宅)とで異なります。
居住部分に係る床面積の120m2を限度(120m2を超えるものは120m2相当分まで)として減額の対象となります。
減額期間は、3階建以上で耐火構造の住宅の場合は5年度分、それ以外の住宅に関しては3年度分です。
居住部分に係る床面積の120m2を限度(120m2を超えるものは120m2相当分まで)として減額の対象となります。
減額期間は、3階建以上で耐火構造の長期優良住宅の場合は7年度分、それ以外の長期優良住宅に関しては5年度分です。
固定資産税の納税義務者について
固定資産税の納税義務を有する者は、固定資産を所有している個人と法人です。具体的には次の表のとおりです。
【土 地】原則、登記簿や土地補充課税台帳に、所有者として登録されている者
【建 物】原則、登記簿や家屋補充課税台帳に、所有者として登録されている者
【償却資産】原則、償却資産課税台帳に、所有者として登録されている者
ちなみに、総務省ホームページからの情報によると、2022年度(令和4年度)固定資産税の納税者は、土地:4,155万人、家屋:4,237万人、償却資産:483万人と発表されています。
資産譲渡後(年の途中で資産の売買等が行われた場合)の納税義務者について
固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)時点で登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われた場合でも、納税義務者は変更されませんので、固定資産税の納税通知書は、1月1日時点の所有者宛に送られてきます。
なお、売買契約などで所有権移転をする際に、固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものとなります。
この件に関して、不動産会社の視点でお伝えさせていただくと、不動産売買の実際の現場では、売買代金の支払いと物件の引渡し(所有権移転)が行われる決済時に、固定資産税の日割り清算が行われるケースが殆どです。
固定資産税の納付先
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産が所在する市町村に「市町村税」として納付します。
ただし、東京都23区内の場合は、東京都に対して「都税」として納税することになります。(東京都の多摩地域、島しょ地域にある固定資産については市町村に納めます)
固定資産税の納付時期
さて次に、固定資産税の納付時期についてです。
地方税法によると、固定資産税の納期は「4月、7月、12月及び(翌年)2月中において当該市町村の条例で定める」と規定されていますので、全国的には地方税法に則った納期を設定している自治体が多いようです。
但し、「特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」との例外も認められているため、異なる時期を設定している自治体もあります。ちなみに、東京23区の納期は、「6月、9月、12月及び(翌年)2月」となっています。各自治体によって納付時期が異なりますので、固定資産税の納税通知書がお手元に届きましたら、まずはご自身できちんと納期の確認を行うようにしましょう。
固定資産税は、金額が高額になることも多いため、納付については前述のとおり原則年4回に分けられています。しかし、この納付回数については、地方税法に「固定資産税額が、市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によって定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる」と記載されていますので、納税者が希望すれば、第一期(1回目の納付)のときに全額を一括で納付することも可能となっています。
固定資産税を滞納したらどうなるのか
それでは、固定資産税を定められた納期限までに支払えず、滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか。固定資産税を滞納したあとの流れについて確認していきます。
まず、固定資産税を滞納したからといって、すぐに本人に対して不利益が生じるわけではありません。しかし、滞納が長期間続くようなことになると、最終的には債権者(役所など)が強制執行に踏み切り、固定資産が公売にかけられる可能性があります。
但し、そこに至るまでには、以下のように一定の手順が踏まれることが一般的です。固定資産税の期限通りの納付が難しい場合には、その段階で早めに役所に相談してください。相談することもなく、納税にも応じないような場合には、いずれ固定資産は公売にかけられ、その売却代金で支払いをすることになります。
督促状が届く
固定資産税には、納期限が設けられているため、納期限を過ぎても納付されない場合は、滞納扱いとなり督促状が送られてきます。
督促状には、固定資産税が滞納となっている旨、滞納額の支払いを請求する旨などが記載されています。そのため、督促状を受け取った場合には、可能な限り早期に納付を行い、滞納を解消することが望ましいです。
また、滞納を解消することが困難な場合であっても、役所に連絡を入れて状況を説明するなどして誠実に対応することが求められます。
財産調査
督促状が送られてきているにも関わらず支払いに応じなかったり、役所に連絡を入れることもせずに放置し続けていたりすると、徴収職員により財産調査が開始されます。
ここでいう「財産調査」とは、滞納者がどのような財産を保有しているかを把握するために行われる調査のことをいいます。
税金等の滞納処分における財産調査は、「国税徴収法」という法律によって認められているものです。そのため、財産調査が開始されると、就業先や預貯金口座など、滞納者の勤務先や保有する財産などは、すぐに突き止められてしまいます。
不動産などの財産を差押えられる
財産調査により滞納者に財産があることが判明すると、次はその財産についての差押えが行われます。
差押えの対象となる財産は、不動産のほかにも預貯金口座や給与などがあります。滞納している額にもよりますが、滞納者の財産を差押える場合には、預貯金や給与から差押えることが多いようです。不動産を差押えるよりも、手続きの面において簡易かつ時間もかからないためです。
公売にかけられる
不動産を差押えられた場合、その不動産は公売にかけられ、最終的に第三者に売却されることになります。この段階に至ってしまうと、競落した第三者から不動産を取り戻そうとしてもできません。
このように、滞納者自身での対処が遅れてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。固定資産税を滞納した場合には、取り返しがつかなくなる前に、適切に対処することが必要です。
固定資産税の延滞金について
固定資産税に限らず税金の場合は、法定納期限の翌日から延滞金が発生します。つまり、税金を滞納すると、滞納金対して一日ごとに「延滞金」も追加で加算されていきます。
この延滞金に関しては、滞納期間によって税率※1が変わってきますので、滞納期間が長くなればなるほど高額になってきます。
具体的には、以下のとおりです。
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:年2.4%
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後:年8.7%
延滞税の割合は、毎年見直しが行われます。詳しい算出方法や過去の税率などを確認されたい場合は、こちらよりご確認ください。(国税庁ホームページへ移行します)
なお、督促状が届いた時点で、滞納額に延滞金を足して納付を行えば、滞納を解消することができます。
固定資産税の支払いは免除されない
税金を滞納する原因の中で最も多いのが、他の「借金」ではないでしょうか。
借金の返済が困難になると、場合によっては自己破産をするほかなくなりますが、このときに注意しなければならないのが、税金はその支払いを完納するまで免除(免責)されないということです。
借金をチャラにするための手続きである「自己破産」においても、税金は非免責債権として扱われます。そのため、滞納している固定資産税については、自己破産するしないに関係なく、全額納付しなければばりません。完納されるまで債権者(役所等)からの督促は続きます。
固定資産税を滞納した際の対処法について
固定資産税を滞納してしまった場合、できるだけ早期に対処する必要があります。
経済的に厳しい状況に置かれている滞納者も少なくないため、役所などでは以下のような対処法を設けています。滞納者は、早めに役所などに相談をして自身に適した対処法を選択することが大切です。
分納
固定資産税を滞納した場合において、滞納額を一括で支払うことができる人は多くありません。この場合、役所の職員に相談することで分納を認めてもらえる可能性があります。
「分納」とは、言葉のとおり、滞納額を分割して支払っていくことをいいます。具体的な分納額については、慎重に決定する必要があります。職員と相談のうえ決定することになりますが、確実に支払っていくことができる金額を分納額として設定することが重要です。
分納を認めてもらえたにもかかわらず、再度途中で支払いを怠ると、財産を差押えられる可能性が高まりますので注意するようにしましょう。
徴収猶予
「徴収猶予」とは、固定資産税の納付について猶予を受けられる制度です。
最長で1年間猶予を受けることができますが、徴収猶予を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 災害等により、納税者において財産上の損失を受けた場合
- 災害や病気、事業の休廃止等により、税金を納付できない場合
前者については、納期限が到来していないものに限られているため、滞納している固定資産税については対象となりません。
徴収猶予を受けることによって延滞金を免除してもらえるケースもあり、また、猶予期間中においては財産を差押えられることはありません。
換価の猶予
「換価の猶予」とは、財産を差押えられた場合に、その換価につき一定期間の猶予が受けられるという制度です。
換価の猶予を受けるためには、たとえば、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 滞納額を一括で支払うことにより、事業の継続や生活の維持が困難になる恐れがある場合
- 滞納者が納税に関して誠実な意思を有すること
- 他の税金について滞納がないこと
この他にもいくつかの条件があり、換価の猶予については、誰もが簡単に利用できる制度ではありません。
たとえば、督促状が送られてきた際に、その状況を放置したような経緯がある場合には「納税に関して誠実な意思を有する」とは言えないため、換価の猶予を受けられる可能性は低くなるでしょう。
固定資産税が払えない状況にあるときは早めの対策を
固定資産税を滞納すると、最悪の場合、所有不動産を手放さなければならなくなります。
納税が苦しくなった時には、これまでにも何度もお伝えしているとおり、滞納する前に役所などに相談することをお勧めします。そうすることで、分納や徴収猶予を認めてもらえる可能性が出てきます。
また、今はまだ何とか大丈夫でも、長期的に見た場合に固定資産税の納付を続けることが厳しいと判断した場合には、「任意売却」を検討することも選択肢の一つです。
任意売却では、競売よりも高い価格で不動産を売却できる可能性があり、また、不動産の所有権は失うことになるものの、リースバックによってその不動産に住み続けることができる可能性もあります。
以上のように、固定資産税の滞納については、早めに対策を講じることで、結果として不利益を最小限に抑えることができます。