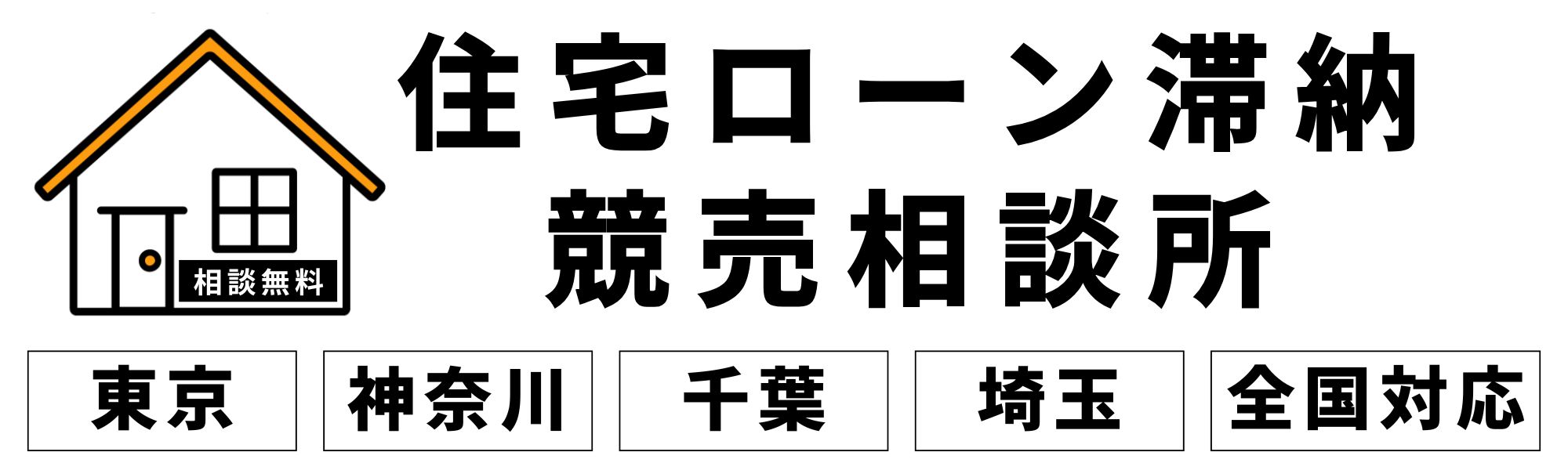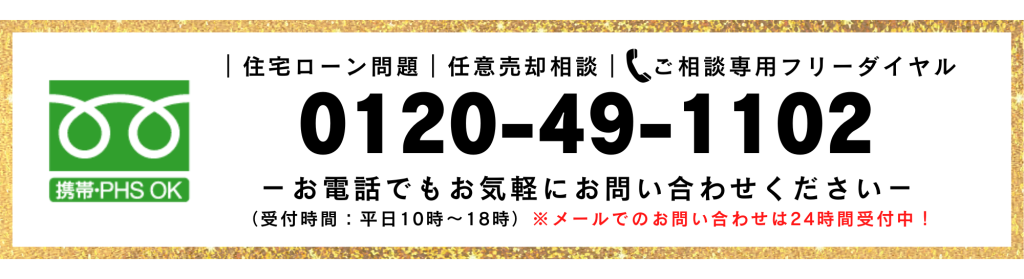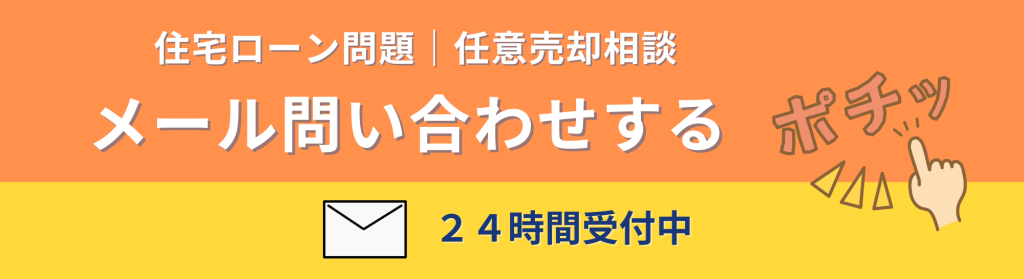競売で売れない不動産はどうなる?再競売・任意売却、後悔しない選択とは

自宅が競売になったのに、誰にも落札されなかった――
そのような状況に直面したとき、競売にかけられた不動産はその後どうなるか、ご存じですか?
実は、競売で不動産が売れなかった場合、「特別売却」や「再競売」といった次のステップに進みます。しかし、それでも売却できないケースもあり、競売は必要以上に大きな損失や後悔を招くこともあります。
この記事では、不動産が競売で売れなかったときの基本的な流れから、特別売却・再競売の仕組み、そして競売を回避する手段である「任意売却」について、あなたが後悔しない選択ができるよう、わかりやすく解説します。
「どうすれば正しい選択ができるのか?」と悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を東京都新宿区に設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
競売で不動産が売れなかったら
「競売が開始されたら、家は手放さなければならない」
そう思われている方も多いかもしれません。
しかし実際には、競売が成立しないケースもあります。買い手が現れなかったり、入札価格が一定の基準に満たなかった場合には、競売は「不成立」となり、別の対応が必要になります。
この章では、競売が成立しないときの理由や、「売却不調※1」となる条件、その後に取られる具体的な対応としての「特別売却」「再競売」について解説していきます。
売却不調とは、競売にかけられた不動産が落札されなかった状態を指します。
入札期日までに誰からも入札がなかったり、最低価格に満たない入札しかなかった場合は売却が不成立となります。
競売が成立しにくい主な理由とは
競売が成立しない背景には、いくつかの理由があります。
主な要因は以下のとおりです。
■物件の状態が悪い/内見できない■
競売物件は現況のまま引き渡されることが多く、内見も基本的にはできません。室内の状態が確認できないことから、購入に慎重になる人が多く、入札が見送られる原因となります。
■立地条件が悪い■
交通アクセスの不便さや、災害リスクの高いエリアなどは、需要自体が低くなりがちです。その結果、買い手がつかず、競売が成立しにくくなります。
■最低売却価格が相場より高い■
裁判所が設定する「最低売却価格」が、地域の市場価格よりも高い場合は、入札者が価格に見合わないと判断して敬遠するケースがあります。
■占有者がいる/明け渡しに不安がある■
物件に元所有者や賃借人が住み続けているケースでは、「退去してもらえるのか」「費用がかかったり、手続きが面倒ではないか」といった不安が出るため、敬遠されやすくなります。
このように、物件の条件や法的リスクが入札者にとって不安材料となると、競売が成立せず「売却不調」に陥る可能性が高くなります。
「売却不調」となったら
競売において「売却不調」とは、買受の申出(入札)がひとつもなかった、もしくは最高入札額が最低売却価格を下回った場合に成立します。売却不調となると、その競売は不成立と判断され、手続きは次の段階へと進みます。
競売には、最低売却価格(=売却基準価額の8割程度)が設定されており、それを下回る価格では裁判所が売却を認めません。たとえ入札があったとしても、この基準を満たしていなければ「不調」とみなされます。
売却不調は、物件の競争力が低いことの表れでもあり、債権者にとっても債権回収が遅れるため大きな課題となります。
その後の流れ|「特別売却」から「再競売」へ
売却不調となった物件については、そこで直ぐに競売が終了するわけではありません。裁判所は、次の手続きとして、まずは「特別売却」を実施します。
さらに、特別売却でも買い手が現れなければ、その次は「再競売」という形で、再び通常の競売手続きが行われます。再競売では、売却基準価額が見直されます。価格が下がることで買い手がつくケースもあるからです。
つまり、不動産競売は次のような流れで進んでいくのが一般的です。
- 競売
↓ - 特別売却
↓ - 再競売
不動産競売では、買い手が見つかるまで「(売却基準価額を下げて)再競売」→「特別売却」の手続きを3回繰り返します。
特別売却とは?通常の競売とどう違うのか
競売が「売却不調」となった場合、ただちに再競売へ進むわけではありません。まず、裁判所が次に行うのが「特別売却」という手続きです。
特別売却は、通常の競売とは売却の方法が異なり、入札ではなく先着順で買受希望者を受け付ける方式です。
少しでも早く不動産を現金化したい債権者にとっては有効な手段のひとつですが、債務者にとっても知っておくべき重要なポイントがあります。
この章では、特別売却の基本的な仕組みから、通常の競売との違い、メリット・デメリット、さらに次へと進む「再競売」の流れまで、詳しく解説していきます。
特別売却の基本的な仕組み
特別売却とは、裁判所が主導する不動産売却の一形態で、通常の競売(入札形式)で売却できなかった不動産を、あらためて売却するための手段です。
大きな特徴は「入札」ではなく「先着順」によって売買が成立する点です。
最低売却価格は変わらず、その価格で購入を希望する人がいれば、原則として先着順で売却が決定されます。
特別売却は期間が限られており、通常、売却不調から1〜2週間程度の間に申込みを受け付けることが多いです。この期間中に買受希望者が現れなければ、物件はさらに次の段階である「再競売」へと進むことになります。
入札ではなく「先着順」の売却方式
通常の競売は、「誰が最も高い価格で買うか」を競う入札方式ですが、特別売却はこれとは異なり、事前に提示された売却価格(=最低売却価格)で購入したい人がいれば、その先着順で売却されるというルールです。
つまり、誰かが「買いたい」と名乗り出れば、他の希望者がいても申込んだ順番が優先されます。入札による価格の上昇がない分、買受人にとってはシンプルで購入しやすい制度となっています。
但し、買主は競売と同様に、物件の現状をそのまま引き継ぐことになります。内部の状態確認が困難だったり、占有者がいる場合など、購入には一定のリスクが伴うこともあります。
特別売却の「メリット」と「デメリット」
特別売却にも、メリットとデメリットがあります。以下に比較してみます。
■メリット■
- 買い手にとっては、価格が明確で交渉しやすい
→先着順のため、時間や競争に悩まされず、スムーズな意思決定が可能 - 債権者・裁判所にとっては、迅速な売却が狙える
→入札の再実施を待たずに、一定の条件で早期に売却できるチャンスがある
■デメリット■
- 債務者にとっては、売却価格に変動がない
→通常の競売と異なり、価格競争が起こらないため、売却価格が上昇する可能性がゼロ - 債務者にとっては、買い手が現れない可能性が高い
→入札と比べて露出が少ないため、そもそも買受希望者が現れず、再競売に進むリスクがある
特別売却でも売れなければ「再競売」へ
特別売却期間中に申込みがなければ、不動産は「再競売」へと進みます。
再競売とは、あらためて競売のスケジュールを立て、最初と同様の手続きを再び行うものです。
このとき、売却基準価額が見直されて引き下げられることが多く、落札の可能性は上がる一方、売却価格はさらに下がる傾向にあります。
債務者にとっては、残債が多く残るリスクがあり、早めに任意売却などの代替策を検討することも重要です。
再競売とは?手続きの流れと注意点
特別売却でも不動産が売れなかった場合、裁判所は「再競売」という手続きを取ります。
これは、最初の競売が不成立だった物件に対して、あらためて通常の競売手続きを最初からやり直すものです。
一見すると再チャレンジの機会のようにも思えますが、再競売には時間的・経済的・心理的な負担が伴うため、債務者にとっては決して軽い選択肢ではありません。
この章では、再競売の基本的な仕組みや注意すべきポイントについて、わかりやすく解説していきます。
再競売の概要
再競売とは、最初の競売手続き(および特別売却)で不動産が売却できなかった場合に、再度、競売手続きを一からやり直す制度です。
通常の競売と同様に、裁判所が売却基準価額を設定し、公告(情報公開)・入札・開札・落札者の決定というプロセスを再び実施します。
再競売に入ると、改めて新しい入札日が設けられるまでの準備期間が必要になり、その間も債務者の精神的負担は続くことになります。また、再競売では物件価値が見直されることが多く、初回競売より売却価格が下がるケースも一般的です。
再競売にかかる期間・コスト・精神的負担
再競売まで進むと、次のような負担がかかる恐れがあります。
■時間的な負担■
再競売が決定されてから実際に入札・落札されるまでには、3〜6か月以上かかることが一般的です。その間、債務者は売却の見通しが立たない状態で不安な時間を過ごすことになります。
■経済的な負担■
競売にかかる費用(評価費用、広告費用など)は裁判所が立て替えた上で最終的に売却代金から回収されます。競売期間が長引けば、その分手続き費用も増加する可能性があります。
■精神的な負担■
再び公告が出され、近隣や知人に競売情報が知られてしまうリスクも高まります。また、落札されるまでは「家を失うかもしれない」という不安が常につきまとうため、生活への影響やストレスが大きくなることもあります。
市場での価値が下がりやすい点にも注意
再競売では、売却基準価額(最低売却価格の元になる価格)が見直されることがほとんどです。これにより、物件の価格は初回の競売よりも下がりやすくなります。
また、不動産市場では「競売で売れ残った物件」としての印象が強まり、買い手に敬遠される傾向もあります。さらに、物件が市場に長期間放置されることで劣化が進み、評価がさらに下がるリスクもあります。
このような理由から、再競売では「ようやく売れたとしても、価格が大きく下がってしまう」という結果になりやすく、債務が多く残る可能性も高くなります。
任意売却という選択肢|競売を避けるもうひとつの道
「競売になってしまったら、もう打つ手はない…」と思っていませんか?
実は、競売にかけられる前、あるいは手続きの途中でも、「任意売却」という選択肢を取ることが可能です。
任意売却とは、債権者(金融機関など)と話し合いながら、通常の不動産売買の形で物件を第三者に売却する方法です。競売よりも高く売れる可能性があり、生活への影響を最小限に抑えられるケースもあります。
この章では、任意売却の基本的な仕組みから、競売との違いやメリット・注意点について詳しく解説していきます。
任意売却の仕組みと競売との違い
任意売却とは、住宅ローンや借入金の返済ができなくなった場合に、債権者の合意を得たうえで不動産を市場で売却する方法です。競売と異なり、任意売却では以下のような特徴があります。
- 市場価格に近い価格で売却できる(買主の選定も可能)
- 引っ越し時期や売却条件について柔軟に調整できる
- 手続きは不動産会社を通して通常の売買と同様に行われる
一方、任意売却には債権者の同意が必要であり、債務状況やタイミングによっては実現できないこともあるため、早めの相談・準備が重要になります。
売却額・残債への影響
競売では、落札価格が低くなりがちなため、売却後に多くの債務(ローンの残り)が残ってしまうケースが一般的です。
一方、任意売却では市場に近い価格で売却できる可能性が高く、残債を少なく抑えることができるという大きなメリットがあります。
また、任意売却後に残った債務についても、分割返済の相談ができるなど、債務整理の面でも柔軟な対応が可能です。
任意売却をしたからといって全ての借金が帳消しになるわけではありません。売却益では返済しきれなかった分の返済義務は残るため、その点は誤解しないようにしましょう。
そのまま住み続けられる可能性
任意売却では、場合によっては「家に住み続ける」という選択肢が残されることもあります。
たとえば、買主が親族や知人である場合、または投資家・投資会社の中には、売却後に賃貸として住み続ける「リースバック」の形を取ることができる可能性もあります。
但し、リースバックはあくまで例外的なケースであり、必ずしも実現できるとは限りません。希望する場合は、早い段階でその可能性を不動産会社や債権者と相談しながら、慎重に計画を立てる必要があります。
「いつまでに判断すべきか」も重要なポイント
任意売却は、競売の入札期日前であれば基本的にいつでも可能ですが、タイミングを逃すと手遅れになってしまいます。
理想的なのは、「競売開始決定通知」が届いた段階、またはその前に動き出すこと。遅くても入札日の1〜2ヶ月前までには手続きを始めるべきです。
任意売却を成功させるには、債権者との交渉、買主探し、売買契約などの準備が必要です。これには一定の時間がかかりますので「なるべく早く相談する」ことが何よりも重要です。
後悔しない選択をするために|自分に合った方法とは
不動産の競売が成立しなかったとき「再競売にかけるしかない」と思い込んでいませんか?
確かに、競売が不成立(売却不調)に終わると、再度の競売を検討するケースが多いですが、それだけが選択肢ではありません。
実際には「特別売却」「再競売」「任意売却」など、いくつかの対応方法があります。そして、その中から自分の状況や希望に合った方法を選ぶことこそが、後悔しないための第一歩です。
この章では、自分にとって最適な選択肢を見つけるための考え方や判断基準を整理していきます。
目的(少しでも高く売却したい・住み続けたい等)による選択軸
選択をする前に、まず考えておきたいのは「自分が何を重視したいのか」という目的です。
たとえば、以下のような目的が、判断の軸として挙げられます。
(目的)なるべく高く売却して残債を減らしたい
▶任意売却のほうが、市場価格に近い金額で売れるケースが多く、残債を減らせる可能性が高いです。
(目的)家に住み続けたい/生活を大きく変えたくない
▶リースバックを活用できる任意売却が選択肢に入ります。但し、ハードルはかなり高いと思ってください。
(目的)手続きの手間を避けたい/割り切って家を手放したい
▶依頼先の会社が手続きを代行してくれる任意売却をお勧めしますが、再競売をそのまま待つという判断もひとつの選択肢です。
このように、「何を優先するか」でベストな選択は変わります。自分の本音や家族の意向を整理することが、後悔のない判断につながります。
状況の整理と専門家活用のすすめ
次に重要なのが、自分の状況を客観的に把握することです。
- どれくらいのローンが残っているのか?
- 現在の収入で返済は可能か?
- 債権者との関係性(交渉の余地)はあるか?
- 入札日はいつか?タイムリミットは?
これらを正しく整理するには、弁護士や任意売却に精通した不動産会社、住宅ローン相談の専門家の力を借りることが有効です。
特に任意売却を検討する場合は、債権者との調整や買主の確保、スケジュール管理が必要になるため、専門家のサポートがあると手続きが格段にスムーズになります。
「再競売」と「任意売却」を比較検討する際のポイント
| 比較項目 | 再競売 | 任意売却 |
| 売却価格 | 最低売却価格ベース (安くなりやすい) |
市場価格に近い (高く売れやすい) |
| 売却までの柔軟性 | 裁判所主導のため調整不可 | 条件・時期の調整が可能 |
| 住み続けられる可能性 | ほぼ不可 | 可能性あり(リースバックなど) |
| 精神的な負担 | 長期化しやすく負担大 | 比較的少ない |
| 専門家の関与 | 裁判所手続き中心で関与少 | 必須(不動産会社・弁護士など) |
このように比較すると、任意売却のほうが柔軟でメリットが多いように感じられますが、すべてのケースに当てはまるとは限りません。時間や債権者の意向などにより、再競売を選ぶほうがスムーズな場合もあります。
重要なのは、「どちらが自分の目的と状況にマッチしているか」を丁寧に見極めることです。
まとめ|売れなかったときこそ「次の一手」は冷静に選ぶ
競売で不動産が売れなかった場合、ショックや不安から思考が止まってしまいがちです。
しかし、「売れなかった=終わり」ではありません。むしろ、次の選択が将来を左右する大きな分かれ道になります。
- 特別売却でチャンスを狙うか
- 再競売を待つか
- 任意売却で自分から動くか
それぞれにメリット・デメリットがありますが、冷静に目的を整理し、専門家と相談しながら判断することが、後悔のない最善の選択につながります。
「どうせ売れないだろう」とあきらめる前に、「どうすれば最小限の損失で未来をつくれるか」を考える視点を持って、ぜひ前向きに次の一手を検討してみてください。
📞「再競売or任意売却」で迷ったら|まずは専門家に無料相談!
株式会社いちとりは、東京都新宿区にある任意売却専門の不動産会社です。
状況は一人一人違います。競売で売却できなかった不動産についても“次の一手”を一緒に考え、アドバイスいたします。まずは、株式会社いちとりにご相談ください。