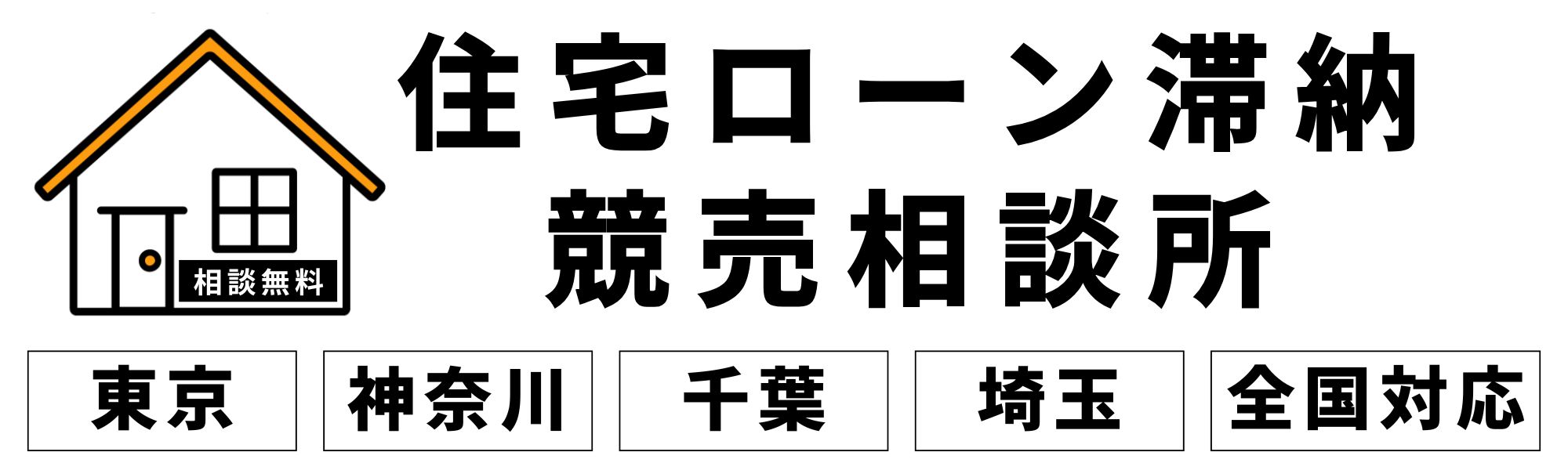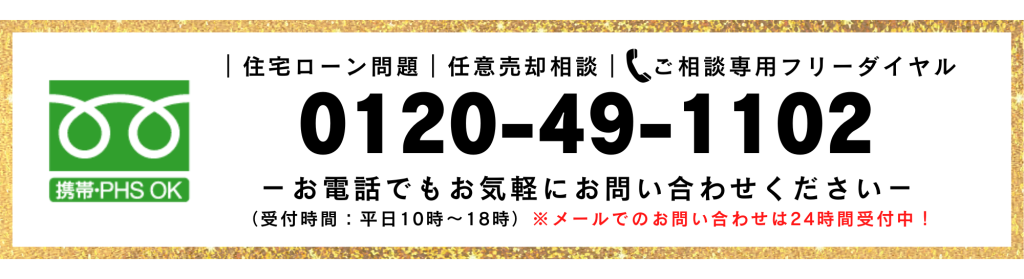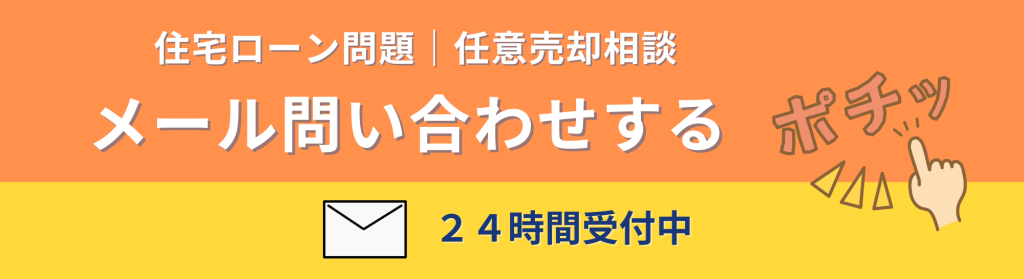強制競売とは?流れ・回避策・取下げ方法までを完全解説【保存版】

強制競売とは、住宅ローンの滞納や債務整理の失敗、裁判で支払い命令を受けたにもかかわらず支払いができなかった場合などに、不動産が差押えられ、裁判所を通じて売却される手続きです。
この記事では「強制競売」に焦点を当て、基本的な仕組みや手続きの流れ、競売に至る原因、そして強制競売を回避・取り下げるための具体的な対策(任意売却や債務整理など)について、初心者にもわかりやすく説明します。「住宅を守りたい」「競売を避けたい」と考えている方のために、今すぐできる行動を一緒に整理していきましょう。

株式会社いちとり
代表取締役/代表相談員
林 達治
東証一部上場不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社を経て、日本全国の不動産を対象とした任意売却を専門に扱う「株式会社いちとり」を東京都新宿区に設立。
勇気を出して相談してくださったご相談者様に最後まで寄り添ってサポートすることを信条に、現在も会社代表を務めながら代表相談員として、住宅ローンの悩みを抱える方々の問題解決のために精力的に活動している。
長年培ってきた任意売却に関する豊富な知識と経験を活かして、個人・法人問わず、年間500件以上の相談を受けており信頼も篤い。
債権回収の手続きとしての競売とは?強制競売と担保不動産競売の概要
競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類がありますが、その違いをご存じですか? どちらも債権者による債権回収の手続きですが、目的や手続きの内容には違いがあります。ここでは、2つの競売の特徴や違いについて説明します。
強制競売とは?|強制競売が行われる主な原因
強制競売とは、借金の返済ができない場合に、債権者が裁判所を通じて債務者の財産を売却する手続きです。特に、抵当権を持たない債権者が確定判決や和解調書などの「債務名義」に基づいて申立てを行うことが多く、競売は裁判所が強制的に実施します。たとえば、裁判で支払い命令が出たにもかかわらず債務者が履行しない場合などによく利用されています。
債務名義|具体的にはどんなもの?
債務名義(さいむめいぎ)とは、債権者が強制執行(差押えや競売など)を行うための「法的な根拠」となる文書のことです。つまり、「この債権は法的に確定している」と証明する“裁判所のお墨付き”のようなものです。
代表的な債務名義には、以下のようなものがあります。
| 債務名義の種類 | 内容・発生のタイミング | |||
| 確定判決 | 裁判で「支払え」と命じられた判決が確定したもの | |||
| 和解調書 | 裁判上の和解が成立した記録 | |||
| 調停調書 | 調停手続きで当事者が合意した内容 | |||
| 公正証書(強制執行認諾文言付き) | 「支払いができなければ強制執行されても異議はない」と明記された公正証書 | |||
| 仮執行宣言付き判決 | 判決が確定する前でも仮に強制執行を可能にする判決 | |||
債権者が、債務者の財産を差押えたり、強制的に売却(競売)したりするには、裁判所が「その請求は正当」と認めた証拠が必要です。それが債務名義です。
たとえば、「あの人に100万円貸したのに返してもらっていない」だけでは強制執行はできませんが、裁判で「返す義務がある」という判決が出たら、強制的に回収できるようになります。(=債務名義の獲得)
担保不動産競売とは?|担保不動産競売が行われる主な原因
担保不動産競売とは、抵当権を持つ債権者が申立てを行い、裁判所を通して不動産を強制的に売却する手続きです。一般的に「競売」と言われる場合はこの担保不動産競売を指すことが多く、実際に行われる件数も強制競売より圧倒的に多くなっています。
主に住宅ローンの返済が滞り、ローン残債が残っている場合に実施され、不動産の売却代金は債権の回収に充てられます。住宅ローン滞納で困っている方にとっては重大な局面となるため、事前の対策や任意売却などの選択肢をしっかり検討することが大切です。
強制競売の対象になる主な原因
強制競売に至る主な原因は、債務の返済が滞ることです。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
事業資金の借入返済不能
個人・法人問わず、事業ローンが返済できないと資産が差押えられることがあります。
個人事業主や中小企業の経営者などが事業資金として借入れたお金を返済できないと、会社名義・個人名義問わず資産が差押えられることがあります。
保証人としての債務負担
他人の借金の保証人になり返済不能になると、自分の財産が競売対象になります。
他人のローンや借金の保証人になり、主たる債務者が返済不能になると、保証人に請求が及びます。保証人も支払いができないと自身の財産も競売対象になることがあります。
税金や保険料などの滞納(公売)
税金や保険料などを長期間支払わずにいると、所有する不動産などの財産が「公売」に出される可能性があります。
公売は、税務署や市区町村などの行政機関自らが、差押えから売却までの手続きを進める制度です。それに対して競売は、返済を求める債権者が裁判所に申立てを行い、その後は裁判所の管理下で手続きが進行します。
両者は手続きを主導する機関や流れに違いがありますが、いずれも所有者の意思にかかわらず、強制的に財産が処分されるという点では共通しています。
公売情報ホームページ(外部サイトへ移行します)
その他の債務不履行
クレジットカードの債務や消費者金融の返済ができなくなった場合も、最終的に競売対象となることがあります。
クレジットカードの多重債務や、消費者金融などからの借入がかさみ返済不能に陥った場合も、最終的に財産が競売にかけられることがあります。
強制競売は「最後の手段」とされる強制執行の一種であり、そこに至るまでには複数の警告や手続きが行われています。逆に言えば、早期の対応や交渉で、強制競売は回避できる可能性が十分あります。
強制競売の流れと手続きの全体像
債務の返済が滞ると、最終的に「強制競売」に至ることがあります。ここでは、強制競売がどのように進行していくのか、主な流れを段階ごとに説明します。
1.支払い滞納・債権者から督促状や催告書が届く
強制競売の発端は、返済義務がある債務の滞納です。強制競売は、債務者の意思に関係なく、裁判所を通して強制的に不動産を売却する手続きですが、いきなり競売開始決定通知書が届くわけではありません。
まずは、債権者から「督促状」や「催告書」あるいは「内容証明郵便」などが届き、それでも支払われない場合、債権者は法的手段を検討し始めます。そして、確定判決などの「債務名義」をとって強制競売の申立てを行います。
2.強制競売の申立て・裁判所による手続き開始
債権者が裁判所に強制競売の申立てを行うと、裁判所はその内容を審査し、手続き開始を決定します。この段階で債務者(不動産所有者)には「競売開始決定通知書」が届き、強制競売手続きが公式にスタートします。
3.物件調査・評価・公告
裁判所が選任した執行官や不動産鑑定士が、対象となる不動産を実地調査し、評価額を算定します。その後、売却基準価額などが記載された「物件明細書」や「評価書」などが作成され、インターネットや官報に公告されます。ここから誰でも入札への参加が可能な状態になります。
4.入札・開札・売却許可
公告後、一定の入札期間が設けられ、購入希望者が入札を行います。期間終了後に開札が行われ、最高額を提示した落札者が決まります。裁判所が落札者に「売却許可決定」を出すことで、正式に物件の売却が成立します。
5.自宅明け渡しと強制退去の可能性
売却許可決定後、債務者は物件を退去しなければなりません。任意での明け渡しが行われない場合、強制的な立ち退き(強制執行)が実施される可能性があります。これは心理的にも大きな負担になるため、早い段階での対応が求められます。
強制競売が及ぼす影響とは?
強制競売は、単に不動産を失うだけでなく、生活や信用に大きな影響を及ぼす重大な法的手続きです。ここでは、強制競売後に起こり得る3つの主な影響をお伝えします。
1.自宅からの退去タイミングと立ち退き命令
強制競売によって自宅が落札されると、原則として物件を明け渡す義務が発生します。落札者が裁判所に「引渡命令」を申立て、裁判所がそれを認めると、債務者(旧所有者)に対して正式な退去命令が出されます。この命令に従わない場合は、強制執行によって家財道具が運び出され、強制的に退去させられる可能性もあります。退去のタイミングは、売却許可決定後から数週間〜数ヶ月程度が一般的です。
2.残った債務の返済義務
強制競売で得られる売却代金は、市場価格よりも低くなることが多く、借入の残債をすべて返済できないケースが大半です。この差額分は競売後も債務として残り、債務者には返済義務が継続します。
たとえば、借入残金が2,000万円、競売による売却額が1,200万円だった場合、800万円の借金が残るということになります。競売はあくまで「財産の換価手続き」であり、借金を帳消しにするものではない点に注意が必要です。
3.信用情報(ブラックリスト)への影響
強制競売が行われると、信用情報機関にその情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」状態になります。これにより、クレジットカードの作成やローンの新規契約が約5〜7年間できなくなる可能性が高くなります。また、家を借りる際の審査や、スマホの分割払いなどにも影響が出る場合があります。信用情報は個人の「金融信頼度」を示すものなので、将来的な資金調達にも大きな制約が生じる恐れがあります。
強制競売は一度始まると止めることが難しく、財産面・生活面・信用面すべてに深刻な影響を及ぼします。こうした事態を避けるためには、早期の相談と対策が重要です。
強制競売を止める・回避するための選択肢
強制競売は、住宅を失う可能性がある深刻な手続きですが、進行前であれば止める方法もあります。ここでは、主な4つの回避策を紹介します。
1.滞納分の一括返済
競売の申立てが行われた後でも、滞納分を一括返済すれば、債権者が申立てを取り下げてくれる可能性があります。特に、競売開始決定前であれば柔軟な対応が期待できるため、早期の行動が重要です。
2.返済条件の見直し(リスケジュール)
債権者に相談し、返済額の減額や期間の延長を交渉する方法です。誠意ある対応と現実的な返済計画を提示することで、競売回避の余地が広がります。
3.任意売却で市場価格による売却を目指す
任意売却は、債権者の同意を得て市場価格に近い金額で不動産を売却する方法です。競売より高く売却できる可能性があり、引っ越し費用の確保や残債の圧縮にもつながります。周囲に知られにくいのも利点です。
4.債務整理(個人再生・自己破産)の活用
返済が困難な場合には、債務整理を検討するのもひとつの方法です。借金が少額であれば「任意整理」、大きければ「個人再生」や「自己破産」が選択肢になります。自己破産では財産を手放す必要がありますが、借金の免除が可能です。
競売の通知が届いても、まだ打つ手はあります。早めに専門家へ相談し、現状を把握して行動することが、生活を立て直す第一歩です。
強制競売を避けるために今すぐできること
強制競売は、住宅を失うだけでなく、生活や信用にも大きなダメージを与えます。しかし、手続きが完了するまでにはある程度の時間を要するため、早期に行動を起こせば強制競売を避けられる可能性は十分にあります。
ここでは、今すぐ実践できる3つのポイントを紹介します。
1.現状の把握と収支の整理
まず最初に取り組むべきことは、自身の経済状況を正しく把握することです。現在の借金総額、収入、支出、滞納の有無とその金額などを整理し、どのくらいの返済が現実的に可能かを明確にしましょう。家計簿をつけるだけでも、ムダな支出や改善点が見えてくることがあります。
2.早期に弁護士・任意売却の専門家へ相談する
収支の整理ができたら、できるだけ早く弁護士や任意売却専門の不動産会社といった専門家に相談することが重要です。これらの専門家は、任意売却や債務整理、返済条件の見直しなど、状況に合った回避策を提案してくれます。相談が遅れるほど、選択肢は狭まり強制競売のリスクは高くなります。
3.感情ではなく、冷静に行動する
強制競売に直面すると、不安や焦りで冷静さを失いがちです。しかし、感情的に動いても問題は解決しません。家族としっかり話し合い、専門家の意見を聞きながら、冷静に今後の方針を決めていくことが大切です。
強制競売は、決して避けられないものではありません。大切なのは、今すぐ行動すること!まずは、弁護士や任意売却の専門家に相談してみましょう。
まとめ|強制競売は「止めることが可能性な手続き」です
強制競売は、あくまで債務整理の最終手段であり、事前に回避できる道は残されています。不動産の競売開始決定通知が届いても、諦めないでください!
「強制競売の止め方」や「任意売却・債務整理などの選択肢」について正しい情報を得ることで、冷静な判断ができるようになります。一人で悩まず、できるだけ早く弁護士や専門家に相談することで、状況に合った最善の方法を選べる可能性が広がります。
大切なのは、感情的にならず冷静に対応すること。そして、行動の第一歩は「知ること」から始まります。今すぐできる小さな一歩が、大切な住まいや生活を守ることにつながります。
株式会社いちとりは、東京都新宿区にある任意売却専門の不動産会社です。
「借金の返済ができない」「競売開始決定通知が届いた」など、お金の問題で所有不動産に差押えや競売の恐れがある場合には、まずは一度、株式会社いちとりまでご相談ください。