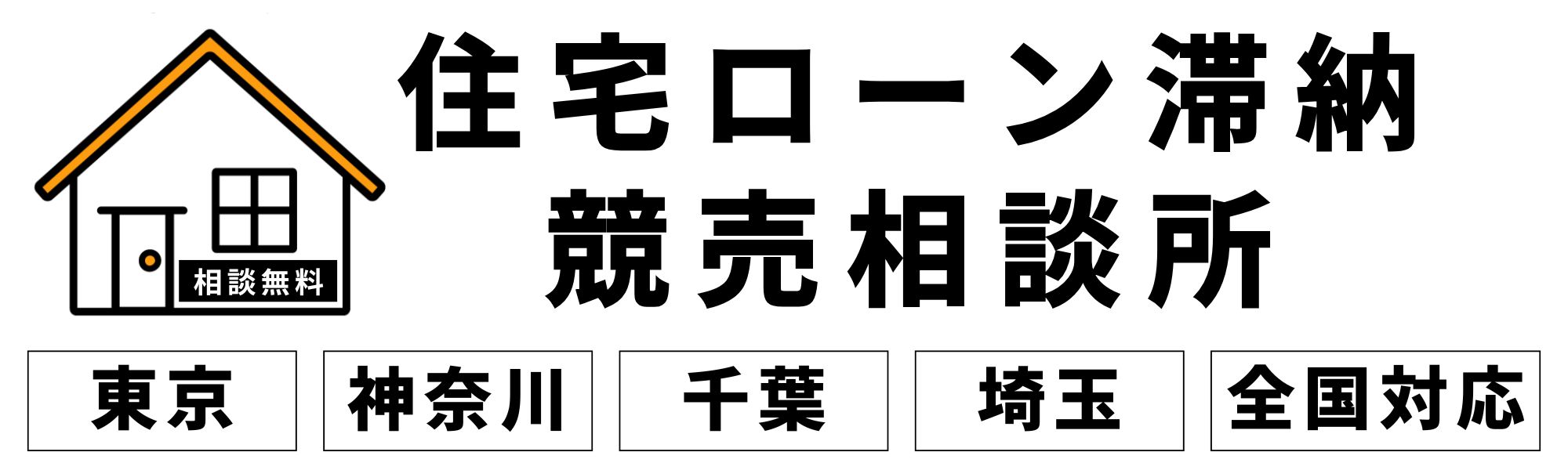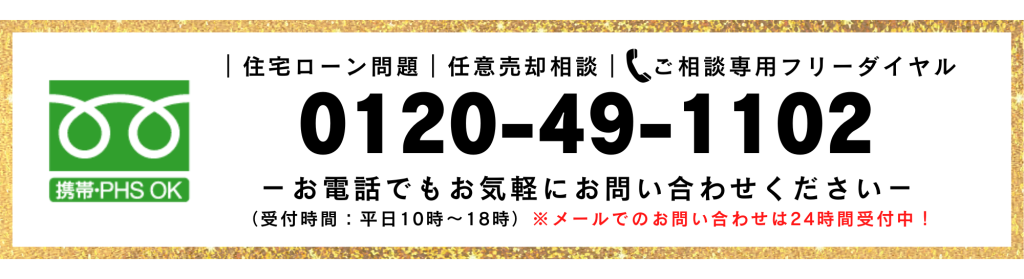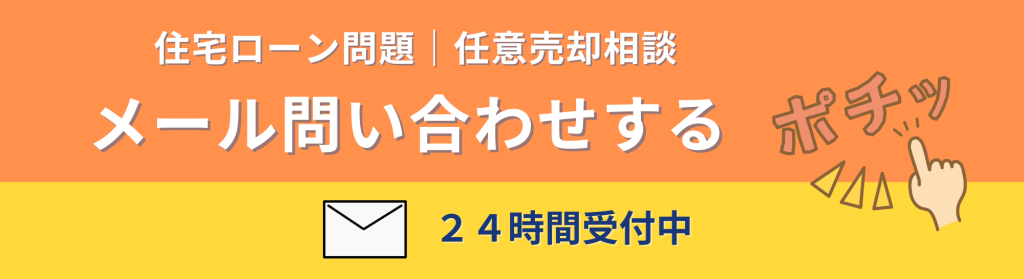競売になると債務が増える!?知らないと損する競売費用の仕組みと対処法

住宅ローンの滞納が続き、ついに「競売開始決定通知書」が届いてしまった――。
そのような状況で、「競売にはどんな費用がかかるの?」「誰が支払うの?」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
不動産競売は、債権者(金融機関など)が手続きを進めるのが一般的なので、その費用は債権者が出すと思われがちです。
しかし実際は、債務者側(競売を申し立てられた側)に費用負担が発生する仕組みになっています。
この記事では、債務者が知っておくべき競売費用の内訳や注意点、そして費用負担をできるだけ抑えるための対処法を、任意売却の専門家がわかりやすく解説します。

住宅ローン滞納・競売相談所
代表相談員|林 達治
東証一部上場の不動産会社、外資系金融機関、任意売却専門会社での豊富な実務経験を活かし、「住宅ローン滞納・競売相談所」を開設。
代表相談員として、住宅ローンの滞納や競売に関する高度な専門知識をもとに、信頼性の高いサポートが全国のご相談者様に喜ばれている。
「勇気を出して相談してくださった方に、最後まで寄り添うこと」を信条に、複雑な問題を抱える方々の不安を取り除きながら、最適な解決策をご提案。
現在では、個人・法人を問わず年間500件以上の相談に対応しており、その実績は業界内でも高く評価されている。
不動産競売の目的と流れ
住宅ローンなどの返済が滞ると、債権者は貸したお金を回収するために、裁判所へ「不動産競売」の申し立てを行います。なぜなら、債権者にとっては貸したお金を返してもらうことが最も重要だからです。
その債権者が、支払い不能に陥った債務者に対して最終手段として行うのが「不動産競売」であり、その目的は債務者が所有する不動産を強制的に売却して現金化し、その代金を返済に充てることにあります。
それでは、不動産競売の一般的な流れを見ていきましょう。
不動産競売の一般的な流れ
滞納が始まってから、不動産競売に至るまでの一般的な流れは次のとおりです。
- 住宅ローンの滞納
- 債権者からの督促・催告
- 裁判所への競売申し立て
- 競売開始決定
- 不動産の差し押さえ
- 裁判所による現地調査・評価・公告
- 入札・開札・売却決定
通常、不動産競売はこのような手順で進められますが、その過程ではさまざまな費用や手続き上の負担が発生します。では、これらの費用は一体誰が負担するのでしょうか。
不動産競売とは?|債務者にとっての意味を整理しよう
今現在、「競売開始決定通知」が自宅に届き「もう終わりだ・・・」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、競売は突然始まるわけではなく、一定の手続きと時間を経て進行しますので、まずはその仕組みを理解することが大切です。
また、不動産競売にはさまざまな手続き費用がかかる点も見逃せません。
「その費用は誰が負担するのか?」「競売を避ける方法はあるのか?」といった不安や疑問を解消しながら、競売の仕組みと債務者への影響を一緒に整理していきましょう。
なぜ、不動産競売が行われるのか?
不動産競売とは、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所を通じて債務者が所有する不動産を強制的に売却する手続きです。
この売却によって得られた代金が、未払いとなっているローン残金や借金の返済に充てられます。
言い換えれば、競売は「どうしても返済ができなくなったときに取られる最後の手段」であり、債務者にとっては大切な資産を失うだけでなく、精神的なプレッシャーも大きなものになります。
しかしながら、競売に至る前に取れる手段もあります。そのひとつが「任意売却」です。
任意売却であれば、債権者の同意を得て自らの意志で不動産を売却できます。
競売よりも高値で売却できる可能性が高く、引っ越し費用の捻出などにもつながるため、経済的にも負担が軽くなるケースが多いです。
競売が開始されるとどうなる?
裁判所から「競売開始決定通知書」が届いた時点で、その不動産は差し押さえの状態となり、所有者が自由に売却や処分することはできなくなります。
さらに、競売の情報はインターネット上でも公開されるため、近隣住民や勤務先などに知られるリスクもゼロではなくなります。
この段階に入ると、時間の経過とともに競売を止めることは難しくなりますが、まだ完全に手遅れといった状況ではありません。
今置かれている状況を正しく理解し、早めに行動すれば、被害や損失を最小限に抑えることは可能です。
競売における費用負担の仕組み
不動産競売は、裁判所を介して進められるため、手続きの各段階でさまざまな費用が発生します。
これらの費用は一時的に債権者が立て替えますが、最終的には債務者に請求され、残った債務に上乗せされる仕組みとなっています。
そのため、「自分には関係ない」と思っていると、想定外の費用負担につながることがありますので、注意が必要です。
不動産競売にかかる主な費用(東京地方裁判所の場合)
不動産競売では、さまざま手続き費用をまずは裁判所へ納めることになります。
これらの費用は、最終的には債務者の負担となるため、競売が開始されることによって債務額が増える可能性が出てきます。
それでは、不動産競売にかかる主な費用をみていきましょう。
1.申立手数料
申立手数料とは、不動産競売を申し立てる際に裁判所へ支払う基本的な費用です。
支払いは、申立書に収入印紙を貼付する形で行います。「担保権」または「請求権」1つにつき4,000円が必要です。
〈例〉
住宅ローンの担保が2つある場合は、
『4,000円×2=8,000円』が申立手数料となります。
- 抵当権:不動産を担保にした借入(住宅ローンなど)
- 根抵当権:限度額内で繰り返し借りられる担保(主に事業者向け)
- 質権:動産や債権を担保にした借入(車、貴金属、有価証券など)
2.予納金
予納金とは、競売の手続きにかかる実費(調査費・公告費・鑑定費など)をカバーするために、裁判所へ事前に納める費用です。
金額は、債権額の規模によって異なります。以下は、おおよその目安です。
| 債権額 | 予納金の目安 |
| 2,000万円未満 | 約80万円 |
| 2,000万円~5,000万円未満 | 約100万円 |
| 5,000万円~1億円未満 | 約150万円 |
| 1億円以上 | 約200万円 |
💡予納金だけでも100万円近い金額になることがあり、この金額が最終的には債務に上乗せされる点に注意が必要です。
3.郵便切手・封筒(裁判所からの通知送付用)
裁判所が債務者や関係者に各種通知を送付する際に必要となる郵送費も、競売費用に含まれます。
一般的には「110円切手×1枚」「長形3号封筒×1枚」など、数百円程度の軽微な費用ですが、送付書類の数が多い場合には、追加費用が発生することもあります。
💡「こんな細かい費用まで?」と思われるかもしれませんが、これらも最終的には債務者の負担となるため見逃すことはできません。
4.登録免許税(差押登記のための費用)
不動産を差し押さえる際には「差押登記」が必要となり、その手続きにかかるのが登録免許税です。
この税金は、請求債権額の1,000分の4(=0.4%)で計算されます。
- 債権額が300万円の場合 → 約12,000円
- 債権額が2,000万円の場合 → 約80,000円
※最低でも1,000円が必要です。
※根抵当権の場合は「極度額(最大借入限度額)」を基準に計算されます。
💡不動産差し押さえのためにかかるこの税金も、最終的には債務者の負担に加わるため軽視はできません。
債務者が注意すべきこと
ここまで紹介した費用は、いずれも債権者が一時的に立て替えて支払います。
しかし、競売で得られた売却代金からは、これらの費用が最優先で差し引かれる仕組みです。
そのため、売却価格が債務額を下回った場合、その差額に加えてこれらの費用分が「債務者の借金」として残ってしまいます。
特に「予納金」は数十万円〜100万円以上になるケースも多く、「自分は支払いをしていないのに、最終的に負担していた」という事態に陥ることもあります。
💡不要な費用負担を避けるためには、競売が進む前にできるだけ早く行動することが重要です!
競売で起こりやすい費用トラブルと注意点
競売の手続きが進む中で、多くの債務者が見落としがちなのが「費用トラブル」です。
「知らなかった」「聞いていない」では済まされない支出が発生し、思わぬ形で債務が増えてしまうケースも少なくありません。
ここでは、実際に起こりやすいトラブル事例を紹介します。
競売費用が後から「借金」になるケース
競売にかかる費用(申立手数料、予納金、登録免許税、郵送費など)は、一旦、債権者が立て替えて支払います。
しかし、物件の売却代金からこれらの費用が差し引かれた後の残額が、債務の返済に充てられる仕組みのため、競売が終了した後に、債務がさらに増えてしまうという状況に陥ることもあります。
想定より安く落札されてしまい、差額負担が発生
競売は、市場価格よりも2〜3割ほど低い価格で落札されることが一般的です。
そのため、想定していたよりも安く落札されてしまうと、残債や競売費用がより多く残り、債務者にとってさらなる負担が生じるケースがあります。
複数の債権者による費用の積み重ね
住宅ローン以外に、税金滞納による差押えや複数のローンが設定されている場合、それぞれの債権者が別々に競売を申し立てることもあります。費用はその都度発生するため、債務者の負担が想定以上に膨らむ恐れがあります。
具体的には、
- 申立手数料の重複
- 登録免許税の加算
- 複数の予納金の負担
など、二重三重に費用が発生してしまうこともありますので注意が必要です。
調査・明け渡し費用など、想定外の実費
競売後の不動産には、次のような費用が発生するケースもあります。
- 室内残置物の撤去費用
- 明け渡し交渉のための弁護士費用
- 立ち退き拒否への対応費用(場合によっては強制執行)
💡これらは通常の競売費用とは別で、債務者に直接請求される可能性がある点に注意が必要です。
競売の費用トラブルを避けるための3つのポイント
競売には「売却されるだけ」では済まないさまざまな費用トラブルが潜んでいます。
特に多いのが、「競売が終わっても借金が減らない」「費用がかかるとは知らなかった」といった声です。
こうしたトラブルを避けるには、競売の仕組みと対処法を早い段階で理解しておくことが何より重要です。
ここでは、費用トラブルを回避するための具体的な3つのポイントをご紹介します。
競売費用の仕組みを早めに理解する
競売にかかる費用は一旦債権者が負担し、最終的には物件の売却代金から差し引かれることで間接的に債務者が負担する仕組みです。
そのため、費用分だけローンの返済に充てられる金額が減り、残債が多く残る可能性があります。
特に予納金や登録免許税などは数十万円〜100万円を超えることもあり、「そんなにかかるとは知らなかった」という声も少なくありません。
こうした仕組みは、事前に理解しておくことで対策が立てられます。安易に放置せず、まずは競売の流れと費用構造をしっかり把握することが第一歩です。
競売前なら「任意売却」が有効な選択
競売開始決定前あるいは決定後でも、入札前であれば、「任意売却」によって問題を解決できる可能性があります。
任意売却とは、債権者の同意を得て不動産を市場価格に近い価格で売却し、その代金を借入金の返済に充てる方法です。
任意売却には、次のようなメリットがあります。
- 売却費用(仲介手数料・抵当権抹消費用など)は売却代金から清算されるため、自己負担は基本的にゼロ
- 競売よりも高く売却できる可能性が高い
- 売却後に残った債務について、分割払いや一部減額の交渉ができる可能性がある
当相談所のような任意売却専門会社では、債権者との交渉から売却完了までを一貫してサポートし、費用負担を抑えながら生活再建を目指すお手伝いが可能です。
💡「もう競売しかない」と思い込む前に、ぜひ一度、任意売却という選択肢もご検討ください。
弁護士・司法書士との連携でより安心に
任意売却や競売回避を進めるうえでは、法律的な判断や手続きが関わる場面も多くあります。
特に、以下のようなケースでは弁護士や司法書士との連携が大きな支えになります。
✔ 任意売却後の残債をどうやって返済するか相談したい
✔ 差し押さえや競売に関する法的手続きを確認したい
✔ 債権者との交渉をスムーズに進めたい
法律の専門家と協力することで、トラブルを未然に防ぎ、自分に合った再出発の方法を選択できます。
当相談所でも、ご希望に応じて提携弁護士や司法書士のご紹介が可能です。お一人で悩まず、まずはご相談ください。
まとめ|早めの相談が、費用と不安を最小限に抑えるカギ
不動産競売では、手続きにかかる費用だけでなく、明け渡しや債務整理など、目に見えないコストや精神的な負担も発生します。
しかし、競売が始まる前に行動を起こすことで、こうした負担を大きく減らすことが可能です。
「このまま競売になるのは避けたい」
「できるだけ費用を抑えて解決したい」
そう感じたら、まずは専門家に相談してください。早期にご相談いただくことで、選べる選択肢の幅も広がります。
「住宅ローン滞納・競売相談所」では、任意売却を通じてご相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決プランをご提案しています。
ご相談は無料・秘密厳守ですので、お気軽にお問い合わせください。
📞競売のことでお悩みはありませんか?専門家が無料でサポートいたします|こちらよりお気軽にご相談ください
「住宅ローン滞納・競売相談所」は、東京都新宿区にある任意売却専門の相談所です。
競売にかかる費用、まだ抑えられる可能性があります。放置して債務が増えてしまう前に、早めの相談で最善の解決策を見つけましょう。当相談所のご相談はすべて無料です。ひとりで悩まず、今すぐお気軽にお問い合わせください。